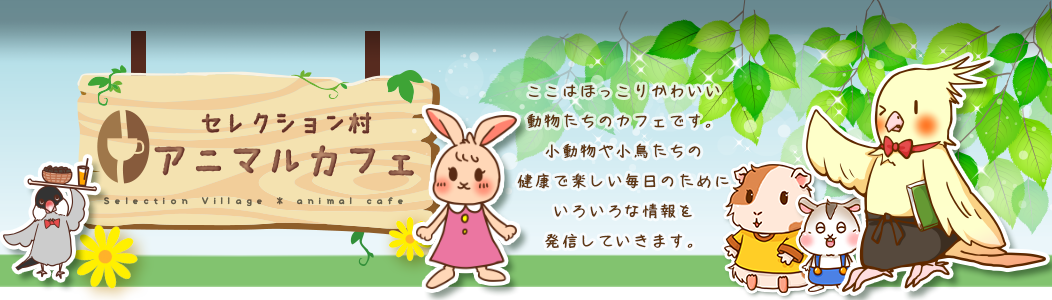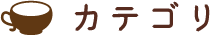大きな耳と立派な尻尾を持ち、体全体が柔らかい被毛で覆われているチンチラ。
今回はチンチラのルーツや体の特徴について詳しく見ていきましょう。

チンチラの生態
チンチラは齧歯目チンチラ科チンチラ属に分類されます。
現在私たちが飼っているチンチラの先祖はオナガチンチラで、
他に野生のチンチラにはタンビチンチラとコスチナチンチラがいたそうです。
野生下では南米のアンデス山脈(現在はチリのみに生息)の西側頂上付近の高地乾燥地帯の岩場に
群れをなして暮らしています。
時には厳しい寒さを避けるために山を降りてデグーの巣穴を借りることもあるそうです。

食性は完全草食性で野生下では木の茎や皮、根、苔など木の実や豆類などより栄養価の低いものを
常食としています。
水分摂取量も少なく、わずかな雪解け水や岩場の水滴などを舐めてしのぎます。
群れの大きさは家族単位の数匹から数百匹の大きなまとまりまで存在します。
チンチラは静かに平和に過ごすことを好むので、他の群れと広く距離をとって暮らしています。
出産は年に2回程度で、1回に産む子供の数は平均2頭と少なめです。
チンチラは野生下では「被捕食者」になります。
天敵はワシ・タカ・フクロウ・キツネ・イタチなどです。
敵から逃れるため必死に岩場を飛び跳ねていたので後ろ足が発達しています。
チンチラの体の特徴
【基本データ】
◆頭胴長:25.4~35.6cm
◆尾長:15.2~20.3cm
◆体重:400~600g
◆寿命:平均して10~15年
(20年以上生きる子もいてギネス記録では29歳229日のチンチラが登録されている。
非公式だが日本には31歳のチンチラがいる*2025年)
密度の高いなめらかな被毛
大変高密度でとても触り心地の良い被毛がチンチラの最大の特徴ではないでしょうか。
個体差はあるものの大体3~4カ月で生え変わり、季節の変わり目の換毛期(年2回)や
ストレスを感じた時などでごっそり抜けて抜け毛が増えます。
艶やかな被毛を保つために皮脂腺から『ラノリン』という物質が次々と分泌されているので
余分なラノリンを除去したり絡まった抜け毛や汚れをきれいにするために
1日1回の砂浴びが必要になります。

一生伸び続ける歯
歯は切歯と臼歯が全部で20本あります。
常生歯で生涯にわたって伸び続けるので不正咬合にさせないためにも
チモシーや餌で摩耗させる必要があります。
正常な切歯の色は黄色や橙色をしていて、真っ白になったときは
体調不良や栄養失調の可能性があります。

完全草食動物
高繊維のチモシーやペレットを主食にしているチンチラは盲腸が大きく、
発達した腸内細菌叢をもっています。
げっ歯類ではありますがウサギと消化管の構造などが似ています。
チンチラは繊細なため食事内容やストレスが原因で消化管の動きが悪くなり
『うっ滞』になりやすいので、普段からしっかり予防する必要があります。
《チンチラの歴史》
古代から毛皮や食肉目的で捕獲されていましたが、チンチラの過剰な捕獲が始まったのは1500年代にスペイン人が原住民であるインカ族を征服してヨーロッパ諸国へ毛皮を送るようになった頃です。
1800年代になると毛皮が世界的に大流行し、1900年代初頭にはチンチラが絶滅の危機になるまで乱獲されました。
1923年にチリの鉱山技師でアメリカ人のチャップマン氏が現地で飼育していたチンチラを本国へ持ち帰り、それらのチンチラが世界で飼育されるチンチラの祖先となりました。日本には1961年にやってきました。
現在ワシントン条約では国際間の取引が禁止されていますが、日本で飼育されているチンチラは国内繁殖のため違法にはなりません。野生のチンチラは絶滅危惧種に指定されています。