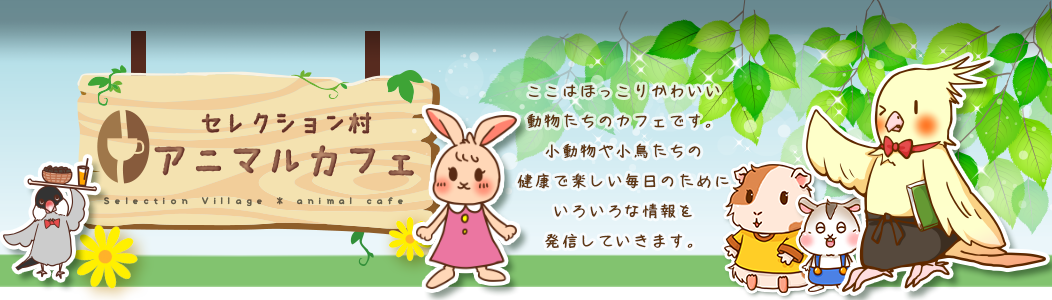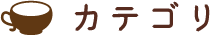インコたちによくみられる病気の1つである“そのう炎”。
皆さんも、一度は見聞きしたことがあるかもしれません。
今回は、“そのう炎”について一緒に学んでいきましょう!
先ずは、“そのう”とはどういうものなのかをご説明します。
『そのう』とは
インコたちは私たち人間がもっていない“そのう”という消化管をもっています。
インコを含め鳥類に見られる消化管で、食道と1つ目の胃の前胃(腺(せん)胃(い))の間にあります。
“そのう”では栄養の吸収は行われず、食べ物を蓄えておく場所いわばご飯の貯蔵庫になります。

しかし全ての鳥類に存在するというわけではなく、
カモメ・ペンギン・フクロウ・オオハシにはありません。
そのうはご飯を貯蔵するだけではなく、ご飯を温めたり摂取した水分でご飯をふやかす役割もあります。
そのうで一時的に貯蔵して柔らかくし、少しずつ1つ目の胃の前胃(腺胃)と2つ目の胃の筋胃(砂(さ)嚢(のう))を通ってさらに、小腸・大腸を通り便となって尿と一緒に排泄されます。
このそのうの機能が低下してしまうと、流れが悪くなって様々な病気の症状が出てきてしまいます…。
その中の1つが、“そのう炎”という病気です。
ここからは、“そのう炎”の原因や症状などをまとめてみたのでみていきましょう。
そのう炎について
原因
細菌や真菌による感染、トリコモナスなどの寄生虫感染であると言われています。
雛では、挿し餌のしすぎによりそのうの流れが悪くなり停滞したご飯の腐敗によってガスが発生しそのう内に充満してしまうことがあります。
また、挿し餌の温め過ぎによる熱傷(電子レンジで温めた場合が多い)、フィーディングチューブによる損傷もそのう炎の原因になります。
*細菌や真菌による感染
細菌や真菌は、インコの常在菌であるため健康な子にも存在しています。
しかし、糖度が高い餌が挿し餌で与えられたり、放鳥時などで人間の食べ物(パンなど)を食べたりして何かしらの原因によって流れが悪くなり食滞が起きて免疫力も低下してしまうと、そのう内で長時間停滞することになり、細菌のバランスが崩れて善玉菌より悪玉菌の数が増えてしまったり、普段より真菌が増殖してしまうために起こります。
症状
食欲不振、吐き気(あくびをすることが多い)、膨羽、体重が減るなどがありますが、嘔吐が特徴的な症状です。

インコたちの嘔吐は、首を左右(水平)に振って吐物を頻回まき散らします。
そのため、頭部や頬など顔の周りの羽毛が吐物で汚れていたり、ケージ内や床に飛び散っていたり餌入れや水入れにも吐物が付着していることがあります。
*発情しているオスのインコは、求愛行動の1つに“吐き戻し”があります。
この場合は、首を縦に振って求愛対象となるオモチャなどに向けて1カ所に吐き出します。
嘔吐とは少し違うので違いをよく確認しておいてください。
治療
一般的には原因となっているものに合わせて抗生剤や抗真菌剤、寄生虫の駆虫薬などを投与し治療を行ないつつ、食事内容の変更やビタミンを与えていきます。
また、食欲がなく食べても直ぐに吐いてしまうことも多いので、しっかりと保温をしながら獣医師の指示のもと口から薬を垂らして投与するか、飲み水に混ぜて投与していきます。
◆もしも発症してしまったら
安静かつ保温が大切になってくるので、あまり動かないようにプラケースや小さめのケージに移し安静にしながら、ケージ内の温度を27℃以上で保温します。
ケージや水入れご飯入れの掃除のポイントとしては、餌入れや水入れはキレイに洗い、ケージは洗った後に熱湯消毒や日光消毒したり、希釈したハイターに漬け置きするのも良い方法です。

◆そのう炎にならないようにするためには
ご飯や水は給餌・給水の時に全量を交換し、腐敗しやすいパンやお米などの食べ物は与えないようにしましょう!
また、雛に挿し餌をしている場合や流動食を与えている場合には、でんぷんや糖を多く含むご飯は避けるようにし、ご飯の温度を温度計でしっかり確認するようにしましょう。
フィーディングチューブでの挿し餌も避けて、挿し餌用のスプーンでの挿し餌を行うようにします。
いかがでしたか?
この病気は嘔吐が特徴的な症状ですが、そのう炎以外の病気でも嘔吐が見られることがあります。
少しでも違和感を覚えたらかかりつけの病院で診てもらうようにしましょう!