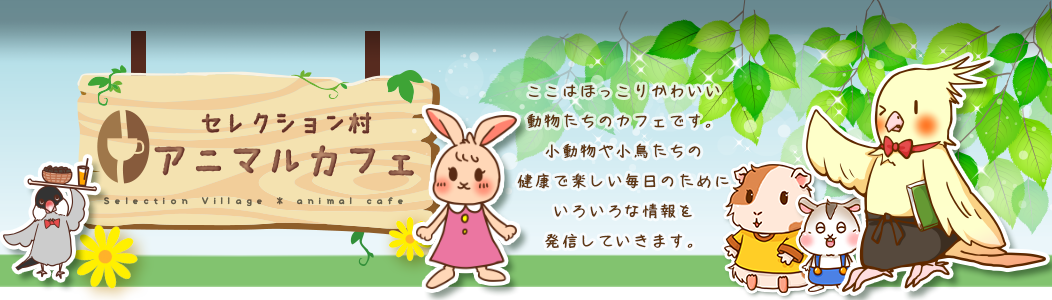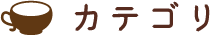動物たちと幸せな日々を送るためには、私たちも動物たちも健康であることが重要です。
しかしいくら気をつけていても病気にかかってしまうことがあります。
その病気の中でも動物と人に共通して感染する可能性がある病気があり、
書籍などでは“人獣共通感染症”・“人畜共通感染症”・“ズーノーシス”、
人から見た場合“動物由来感染症”と呼んだりします。
ではこの共通感染症には一体どのような病気があるのか、
どういった症状がみられるのか一緒に学んでいきましょう!
◎共通感染症とは
『動物⇔人』の間で感染する感染症の病原体には、
ウイルス・細菌・真菌・寄生虫・原虫などがあります。
よく耳にする共通感染症には、
狂犬病・鳥インフルエンザ・新型コロナウイルス(COVID-19)・SARSなどがあります。
では実際に飼育されている動物から人へ感染する恐れがあるのはどのような病気があるのでしょうか?
共通感染症一覧
狂犬病・パスツレラ症・ウサギツメダニ症
野兎病(ツラレミア)・サルモネラ症・ノミ・皮膚糸状菌症
トキソプラズマ症・オウム病・クリプトスポリジウム症
レプトスピラ症・ジアルジア症・ライム病・猫ひっかき病
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など…。
これらの中からいくつかクローズアップし、病気の種類別に症状も纏めていきたいと思います。
◇パスツレラ症

パスツレラ菌という細菌が原因の感染症。
ウサギの鼻腔や副鼻腔に60~70%で常在している菌なのですが健康で免疫力が高いと発症しません。
気温の急激な変化や食事、高齢などによる免疫力の低下がきっかけとなり発症する場合があります。
また犬や猫も保菌していて噛まれたり引っ掻かれたり、
オヤツなどを口移しで与えるなどの過剰なスキンシップでよっても発症します。
*動物の症状:犬や猫では通常、症状が現れることはありません。
ウサギでは、くしゃみ・鼻水(酷くなると膿汁になる)・結膜炎・斜頚・眼振など。
*人の症状:呼吸器に感染すると風邪のような症状、噛まれたり引っ掻かれた場所の腫れや痛み。
◇ノミ

ネコノミやイヌノミが、体の表面に付着して寄生することで発症します。
草が生い茂っている所を散歩したり、私たちが外から持ち込むこともあります。
*動物の症状:痒みを伴い、掻き過ぎてしまうと2次的に細菌性皮膚炎になったりする。
重症の場合は、貧血になることもある。
*人の症状:発疹や痒みなど。
◇皮膚糸状菌症
真菌が原因で、白癬菌(水虫)という単語だと聞きなじみがあるかと思います。
皮膚糸状菌症を引き起こす真菌は、毛創白癬菌・犬小胞子菌・石膏状小胞子菌があり、
人によく感染するのは犬小胞子菌で石膏状小胞子菌は土壌やご家庭のホコリに生息し
接触することで感染します。
*動物の症状:境界がはっきりしている円形の脱毛・フケ・発疹・痒み・皮膚のただれ(びらん)
などが見られる。
これらは、体の至るところに見られ、一度病変ができると急速に拡がる。
*人の症状:多くの場合、顔や頭に見られ、円形の脱毛や痒み、赤くなったりする。
◇サルモネラ症
サルモネラという細菌が原因で、汚染された水や食品(特に生肉)・保菌動物と接触したり、
ペットの排泄物に含まれた菌を口にすることで感染します。
*動物の症状:感染していても症状が出ない場合もあるが、嘔吐や下痢・食欲不振などの症状が
現れることがある。また、幼齢・高齢動物や免疫力が低下していると重症になりやすい。
*人の症状:発熱や嘔吐、下痢などが見られ、幼児や高齢者など免疫力が低下していると重症になりやすい。
◇トキソプラズマ症
トキソプラズマという原虫による感染で、ネコの体内でだけ*有性生殖をおこないます。
感染しているネコは糞便中に”オーシスト”という原虫の卵のようなものを排泄しますが、
その糞便で汚染された野菜、野草や水を口にしたり、公園の砂場などで触れたりして感染します。
*有性生殖…雌雄が交配し子孫を残すこと
*動物の症状:感染していても無症状のことが多い。
しかし、発症すると食欲不振や元気がない、発熱などの症状が見られる。
*人の症状:感染していても無症状のことが多いですが、免疫力が低下していたり妊婦が感染すると
重症になりやすいです。妊娠中に感染すると、胎盤を通して胎児に感染することがあるため注意が
必要です。
◇オウム病
クラミジアという細菌によるもので、感染した鳥の糞尿・鼻汁・唾液などからの
空気感染や接触することで感染します。
日本国内で飼育されている鳥では、セキセイインコ・オカメインコ・ハトで多く報告されています。
また、その中でも幼鳥の保菌率が高くなっています。
*鳥の症状:膨羽・食欲不振・体重の減少・くしゃみ・鼻水など。また、けいれんや斜頚・麻痺などの
神経症状も見られます。
*人の症状:潜伏期間は、1~2週間で突然インフルエンザのような高熱・悪寒・咳・倦怠感などの症状が
現れます。
健康状態に問題がなければ人に感染することは稀ですが、
免疫力や抵抗力が低下している高齢者や妊婦・基礎疾患がある方は注意が必要になります。
◇猫ひっかき病

バルトネラ・ヘンセレという細菌によるもので感染した猫に引っ掻かれたり噛まれたり、
傷ができているところを舐められたりして起こります。
*猫の症状:猫は感染しても症状が出ることは殆どないのですが、長期間は血液中に保菌しています。
*人の症状:感染して3~10日以内に傷口に赤い隆起(皮膚の表面が盛り上がってできるできもの)が
できますが、痛みは伴いません。2週間以内には、脇や足の付け根などのリンパ節が腫れて
痛みが生じ、膿が出ることがあります。
リンパ節が腫れたころから発熱や倦怠感などの症状が見られます。
多くは6~12週ほどで自然に治りますが、免疫力や抵抗力が低下していると
重症化する場合があります。
ここまでは病気や症状について紹介してきましたが、
ここからは予防や対策など私たちができることをまとめてみました。
◎予防・対策
①感染源に接触しない

まず1番重要なのが、“感染源に接触しない”ことです。
外出や散歩の時などに感染源に触れたり、或いは私たちが細菌などを運んでしまうこともあります。
帰宅後手洗いを徹底する・お散歩後は体や足を拭きとる・飼育している子以外の動物との接触は
控えるなどが大切になります。
➁過剰なスキンシップを控える
動物たちはどの子も可愛くて魅力的なので、ついつい触れ合いの度が過ぎてしまうこともあるかと思います。
例えば、口移しで食べ物を与える・頬ずりする・キスをする、など…。
これらのように濃厚に触れ合ってしまうと感染するリスクが高まってしまうので、
節度のある接し方を心がけるようにしましょう!
➂飼育環境を整える
前述した感染症の中には、“感染していても症状が現れない”ものがあります。
これは、動物が健康のときは問題がないけれど体調不良やストレスなどによって、
免疫力が落ちてくると症状が出ることがあります。
・温度湿度の管理
インコ・ウサギ・モルモット・ハムスターなど高温多湿が苦手な動物もいます。
・十分な飼育スペースが確保されているか
ケージの大きさや運動する場所が狭いとストレスになってしまう恐れがあります。
・他の動物や騒音など
ストレスの元凶になりかねません。
・ケージや飼育スペースの清掃
毎日床材の交換や汚れているところを拭いたり、こまめに清掃されているかと思いますが、
時々ケージを丸洗いしたりアルコールや熱湯で消毒することで清潔に保つことができるので
感染症予防になります。

今回は少し難しい内容にはなりましたがいかがでしたか?
これから先も動物たちと楽しく幸せに暮らしていくためにも『動物と人との共通感染症』について
正しい知識と節度のある接し方を心がけていくことが大切です。
もし感染が疑われる場合や少しでもおかしいなと感じたら医療機関を受診するようにしてくださいね。