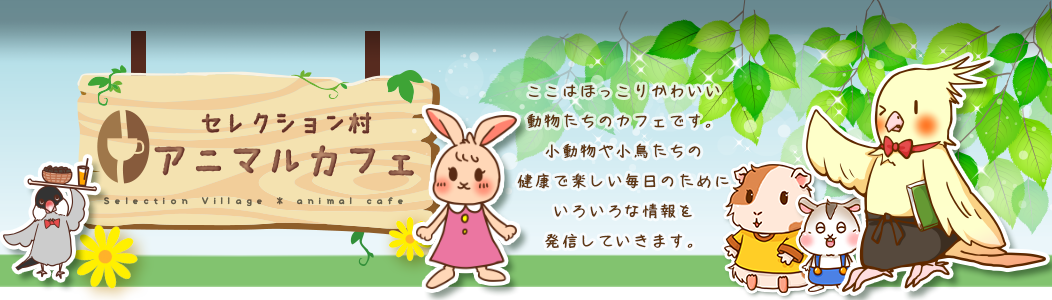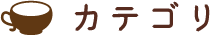ウサギがかかりやすい病気の1つに“尿石症”があります。
今回はその尿石症について、どういった病気なのか・どのように予防したらよいのか、
一緒に学んでいきましょう!
*尿石症って?
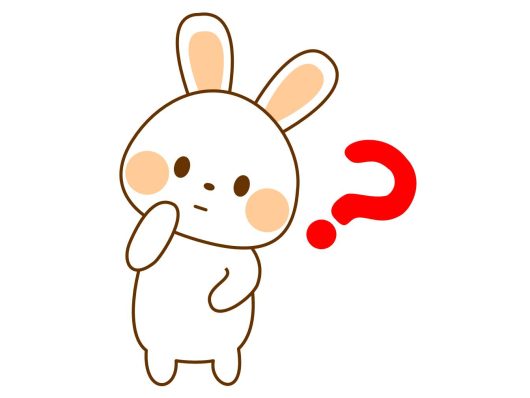
尿石症とは、尿路つまり尿が通るところである腎臓・尿管・膀胱・尿道に
結石*ができる病気で、“尿路結石症”とも言われます。
結石ができた場所によって「尿路結石」「膀胱結石」と呼ばれ、
ウサギの場合は膀胱結石がよく見られます。
また、オスは尿道が長くて詰まりやすいのでオスの方が重度になりやすい病気です。
結石*…尿中のミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)が結晶化して石のように
固まったことでできる「シュウ酸カルシウム結石」と「リン酸カルシウム結石」が
多く見られ、稀に「リン酸マグネシウムアンモニウム(ストルバイト)結石」も
見られます。
*原因
原因ははっきりしませんが、サプリメントやオヤツ・フードによるカルシウムの過剰な摂取や、
カルシウムの代謝が特殊で健康なウサギでも尿中に多くのカルシウムを含んでいるため、
カルシウムの結石ができやすいと言われています。
ウサギの尿について
ウサギの尿は濃く色は白っぽいものから黄色やオレンジ色、また赤色の尿をすることがあります。
濃くて白っぽい尿は、ウサギにとって一般的な尿です。
これはウサギのカルシウム代謝が特殊であるため、炭酸カルシウムを多く含んでいるので白っぽい色をしています。
哺乳類では通常カルシウムは胆汁と一緒に便として排泄されますが、ウサギは尿として排泄されます。
尿中のカルシウム濃度は、哺乳類では2%以下なのに対してウサギは45~60%と高濃度になります!
赤色の尿もウサギではよく見られ、赤くても必ずしも血尿というわけではなく食べ物や水を飲む量が少なくて
尿が凝縮されて赤色っぽく見えることがあるためです。
また、ポルフィリン尿というヘモグロビンが合成されるときに作られるポルフィリンという物質が尿に排泄されることが原因の場合にも赤色っぽい尿が出ます。
関連記事:ウサギの尿をチェックしよう
*症状
結石が詰まらなければ無症状のことがありますが、結石が発生した場所によって症状は様々です。
頻尿(何回も排尿する)、何回もトイレに行く、尿の量が少ない、排尿する姿勢をするけど出にくそう、
排尿時に痛がって鳴く、痛さから背中を丸めたような姿勢になることもあります。
また、じわじわ尿が漏れることでお尻周りが汚れたり、血尿が出たり、痛くて歯ぎしりをしたり
食欲不振になることも…。
結石が尿管や尿道に詰まってしまうと排尿ができなくなります。
そうなってしまうと、血液中の老廃物がうまく体の外に出せなくなって体内に溜まってしまい
尿毒症を引き起こしたり、膀胱破裂や腎不全に進行してしまうと命にかかわる状態となります。
*治療

結石が発生した部位や結石の大きさによって異なってきます。
腎臓や膀胱に結石があっても小さい場合は、点滴で補液をする・飲水量を増やす・利尿剤を投与したりして
自然に排出されるのを促していきます。
しかし、結石が大きく尿管や尿道が詰まってしまっている場合はカテーテルを挿入する治療の他、
手術をして外科的に結石を取り出すこともあります。
これらと並行して、結石を溶かしたり結石の再発を防ぐために食事療法や、
血尿の症状がある場合には消炎剤や止血剤、抗生剤を投与するなどの対症療法も行っていきます。
*予防
カルシウムの摂りすぎや水を飲む量が少なくて排尿する量が減ってしまうことも
原因になってくるので下記のような予防法の例があります。
飲水量
給水ボトルでお水を飲んでいる場合
◇飲み方がわからない
◇ボトル飲み口がウサギに合っていない
◇設置する場所が合っていない
ということがあります。

水をきちんと飲めているのかチェックするようにして、飲み口を届きやすい位置に変更したり、
給水ボトルから飲むのが苦手な子や高齢で顔を挙げるのがつらそうであれば、
水入れを陶器などに変更して平置きにするというのも1つの方法です。
飲み水は、毎日新鮮なものに交換して常に水が飲める状態にしましょう!
食事・おやつ
食べ物に関しては、カルシウムを多く摂り過ぎないように心がけることが大切になります。
カルシウムのサプリメントもありますが、ペレットと牧草だけで必要な栄養素は摂取できるので、
サプリメントは与えなくても問題ありません。
また、牧草の種類も気をつけなければいけません。
マメ科であるアルファルファには、カルシウムが多く含まれているため、
大人のウサギには低カルシウムで高繊維でもあるチモシーがおススメです!
カルシウムを多く含むおやつにも注意し、野菜を与える際には小松菜やチンゲン菜、大根の葉などは
カルシウムが多く含まれているため与えすぎには注意しましょう!

いかがでしたか?
病気になってしまわないためにも、日頃から気にかけてあげること予防に繋がります。
尿の色や回数、普段とは違った行動など見ていて何か気になることがあれば、
早めに病院に行って相談されてみてくださいね。